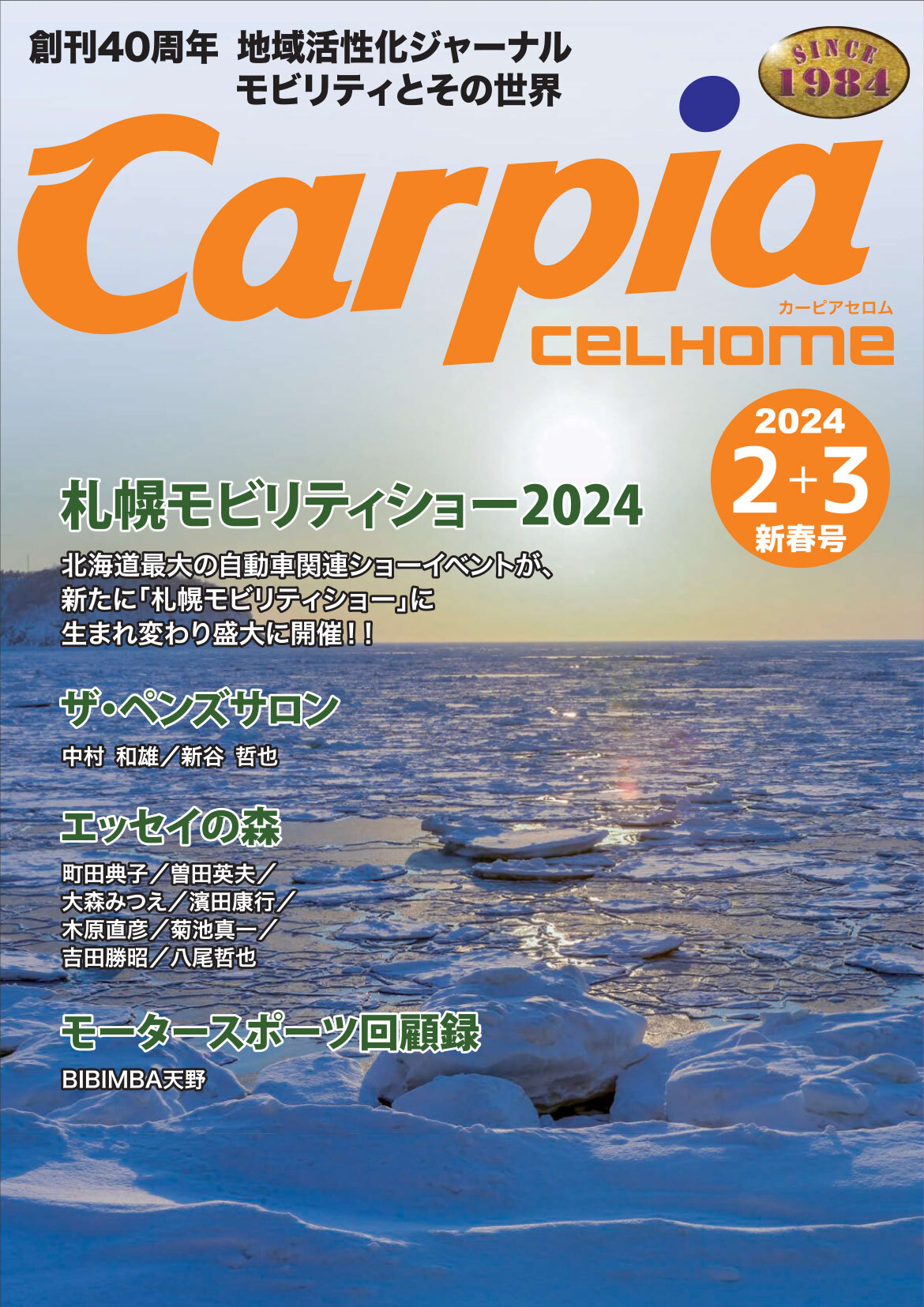カーピアセロム
2024年2月+2024年3月
新春号
巻頭言[北の大地・風を読む]
価値観を認め合うことの大切さ
~イマドキの若者から学んだこと~
★Amazonでも購入できます★
「カーピアセロム」(送料無料、550円・税込)
―カーピアセロムの由来
「カーピア」はカー(クルマ)とピアの合成語。
「セロム」は、ゲーテの人柄をナポレオンをして
「セ・ロム(これぞ、人間だ)」
と言わしめた、伝説の言葉から命名。
出典は、
「詩人ゲーテは職業からいえば弁護士であり、大臣となり、古風な宮廷勤めをソツなくこなし、帝国貴族に列せられ、一目会ったナポレオンをして『セ・ロム(これぞ、人間だ)』と言わしめたほどに底の深い人物であった。
良き友に恵まれ、たえず人と会い、人間が好きで、好奇心と感動する心をいっぱいに備えていた。」
「私のゲーテ:見よ、これが人間だ」より
小塩 節著・青娥書房
今月のオススメコンテンツ
| Ⅰ.クルマ |
|---|
■札幌モビリティショー2024 ■BIBIMBAのモータースポーツ回顧録 その⑧ 『史上最強、超絶ハイテク・ツーリングカーの饗宴! その終焉を看取った舞台は鈴鹿サーキットだった!!』 ※本誌でお楽しみください ■カーピアセロム インフォメーション ※本誌でお楽しみください ■カーピアマンガ フォード 石川 寿彦 ※本誌でお楽しみください |
| Ⅱ.エッセイ | |
|---|---|
■Essay21 最後の同期会から 丹羽 祐而 『龍年に波乱か・変化に対応』 高橋 麗秋 ■いつかの世界通信 第7回 柘 いつか ■青木元の「気象エッセイ」人生色々 お天気色々 第10回 ~地震の揺れを感じない津波~ 青木 元 ■~北海道を元気に!地域の宝物を掘り起こし、よく研け!~ 木村俊昭の「地域創生・SDGs【共創】実践」教室 第6回 木村 俊昭 ■BIBIMBA天野のクルマの楽しみ方流儀 ~番外編 ヤマハこそ"夢"を提供するステキな企業!篇~ 天野 克彦 | ■セ・ロム エッセイの森 町田典子の夢想花②/焦土からの出発 町田 典子 ジョークサロン会員 リレーエッセイ②/川柳で遊ぼう 曽田 英夫 海外旅行の不思議な魅力、私の思い出ガラクタ箱④/ヨーロッパ・スキー 滑るのではなく、ぶっ飛ばす! 大森 みつえ 未来を語る経済学(下) 濵田 康行 木原直彦の風信⑥/北海道独立論 木原 直彦 「高村光太郎と月寒並木」やさしく読みとく⑥/文豪二人が見た札幌 菊池 真一 日経「私の履歴書」執筆者から、注目の北海道人を読む⑤/三浦 雄一郎氏 吉田 勝昭 八尾稔啓のセ・ロム坂龍塾/天災に学ぶ札幌・富山の類似性 八尾 稔啓 ※本誌でお楽しみください ■ザ・ペンズサロン⑱ 未知のビックプロジェクト 中村 和雄 激変する漁業環境にどう臨むか② 新谷 哲也 |
News/最新情報

2024/02/20 new
ホームページ情報をカーピアセロム最新号『2024年2月+2024年3月 新春号』に更新致しました!
★Amazonでも購入できます★
「カーピアセロム」(送料無料、550円・税込み)
2023/09/01 new
2023年10月1日(日)より「適格請求書保存方式(インボイス制度)が導入されます。
弊社は下記の通り登録を完了しておりますので、お知らせします。
登録番号 T7-4300-0100-1699
2023/04/14 new
「北海道自動車関連年鑑」を更新しました。
2021/12/01 new
ホームページをリニューアルしました。
New Car Impression/北海道ステージ
テキスト/横山 聡史
Photo/川村 勲 (川村写真事務所)